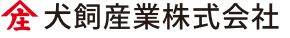社長ブログ
「学問のすすめ」を読んで
06/13/13 10:15:午前先日、義兄に勧められて福沢諭吉の「学問のすすめ」を読みました。
以前読んだと思い込んでいたのですが、内容を見て読んでない事に気づきすぐ読みました。
有名な言葉は皆さん聞いたことのある、「天は人の上に人を創らず、人の下に人を創らず」です。
要は、人は皆生まれながらに平等であるという事ですが、本の内容としてはこの「人」というものはどう有るべきかという事がいろんな角度から考察してあり、なるほどと思う事が書いて有ります。
「人」と「国」の関係、親子など「人」と「人」との関係等々。
個人と国との関係では、“個人の独立があって国の独立がある”という事があります。何があっても国が守ってくれるという事で、例えば、他国が攻めてきた時に国民のそれぞれが、国が守ってくれるからと誰も闘う気がなければ国は守れません。個人が国に依存してしまっていては国の独立も守れないという事です。
すなわち、自分の身は自分で守るという独立心なくして、国の独立は無いという事なのです。
それから、「世話」という言葉の意味もなるほどと思う事がかいてありました。
この「世話」というのには二つの意味があるという事です。それは「保護」と「命令」という事です。
「保護」とは人がやることについて傍らで見守っていて、これを防ぎ護り、物や金を与え、この人の為に時間を費やし、その人の利益や面目を失わないようにする
「命令」とは、その人の為を考え、指図や意見をし、心から親切に忠告をする、
と書いて有りました。
正に、親子又は、国と国民、もしかしたら社長と社員、上司と部下の関係もその範疇かもしれないと思いました。
とにかく、幕末から明治にかけて日本という国を国ならしめる為の人のあり方を説いた「学問のすすめ」、」必読に値すると思います。
一度、是非読んで頂きたいと思います。